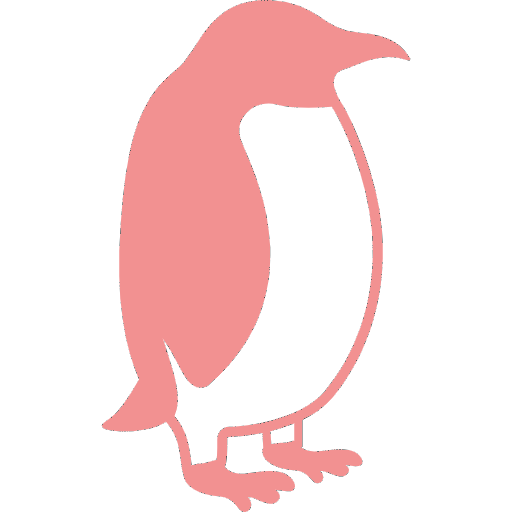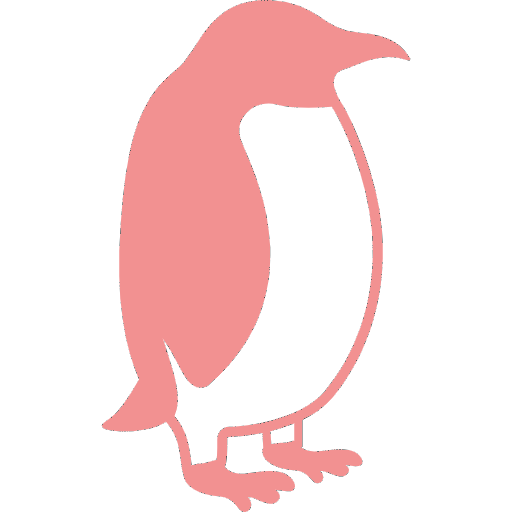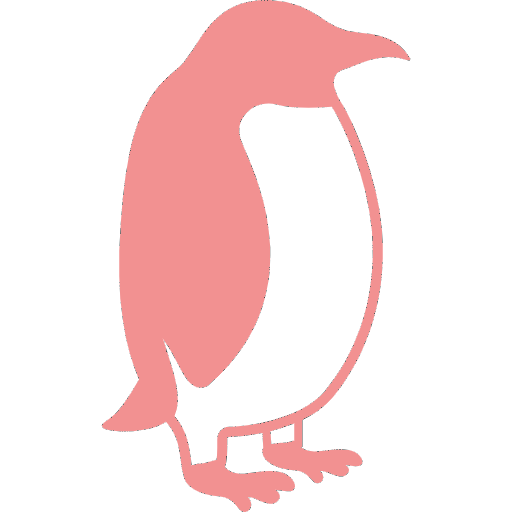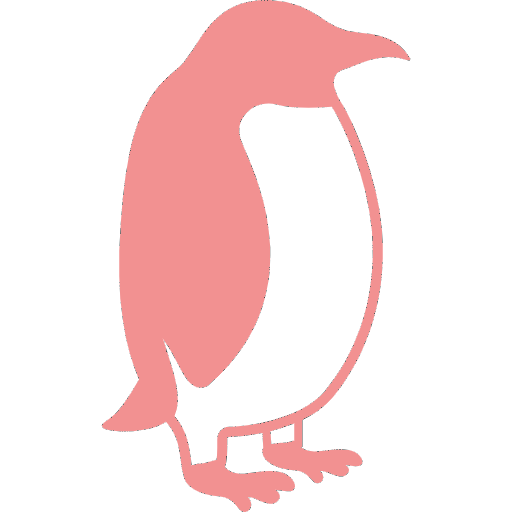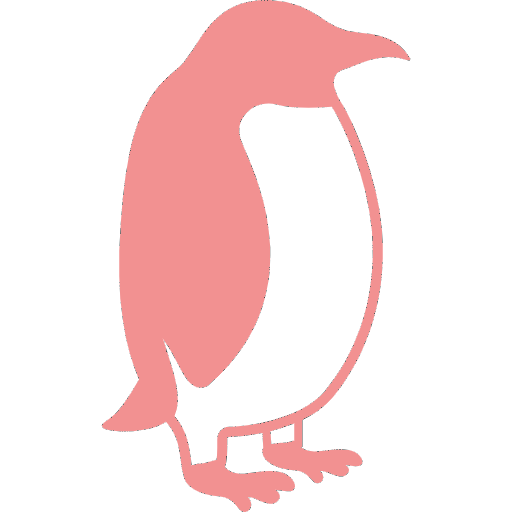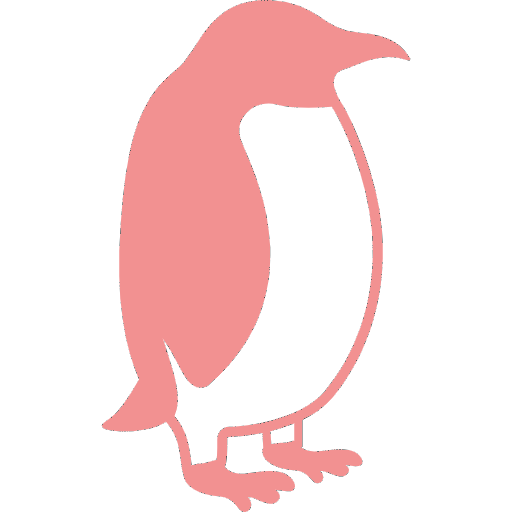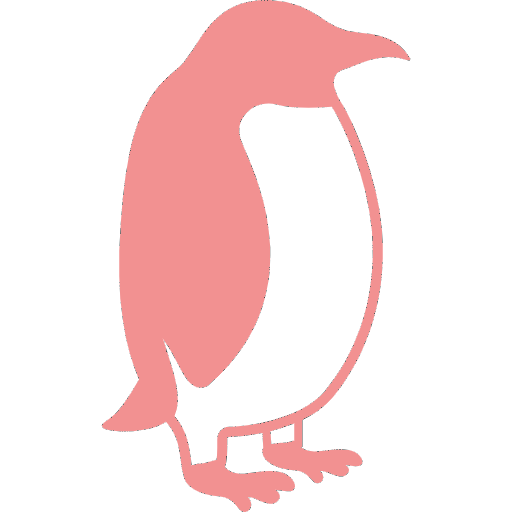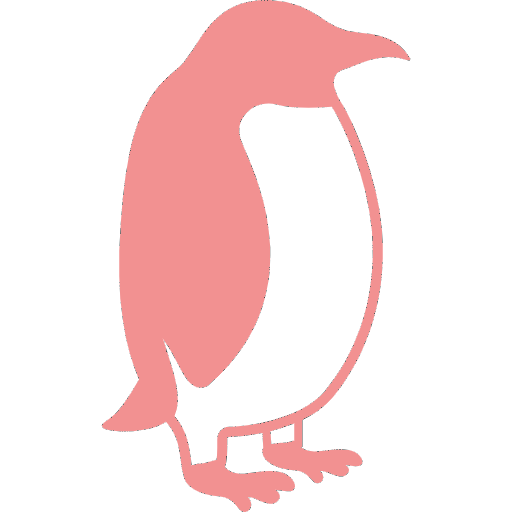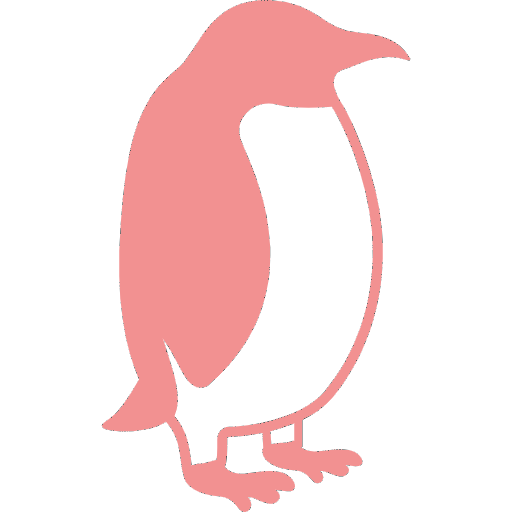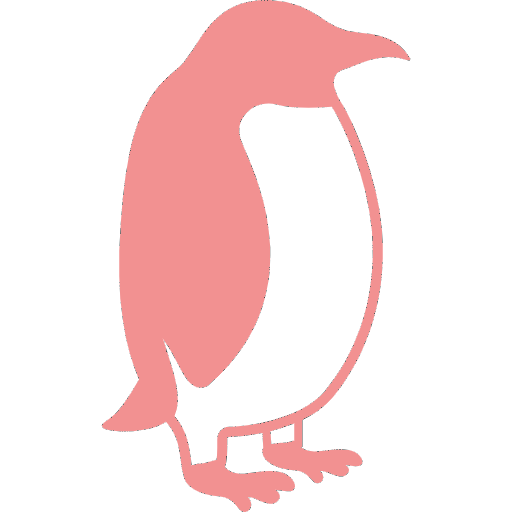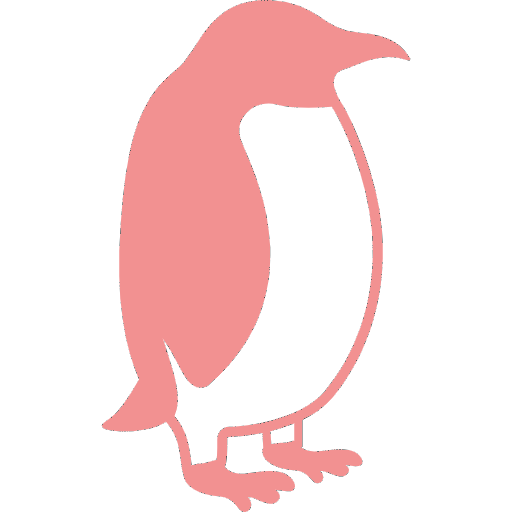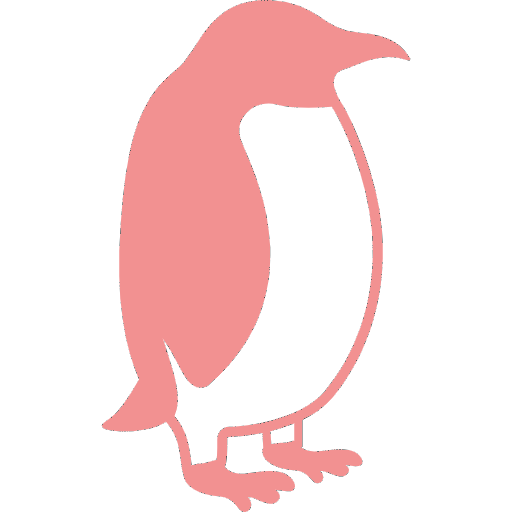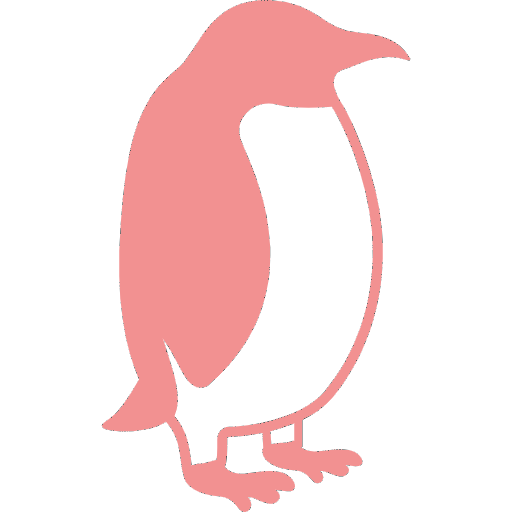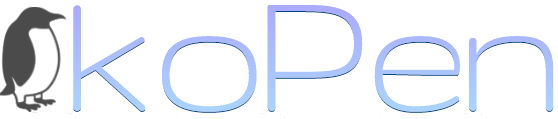K付きモデルではベースクロックに対する内部倍率を自由に変更することができ、メーカーが設定した定格クロックを超えてCPUを動作させる、オーバークロックと呼ばれる設定が可能。
ただし、クロックを上げた状態で動作することが保証されるものではなく、さらにオーバークロックに起因するPCの故障は、メーカーの保証対象外となる点には注意が必要です。
LGA(Land Grid Array)エルジーエー
半導体パッケージの一つで、パッケージの片面に平板なパッド(ランド)を並べたタイプ。
LGA775
PrescottコアのPentium4から採用された775ピンのCPUソケット。ソケットとの接触部分に平たいパッドを並べた形状のCPUパッケージをLGA(Land Grid Array)と言います。
PGA(Pin Grid Array)はパッケージ側のピンをソケット側のホールに挿す構造ですが、LGAはパッケージ側のパッドにソケット側のピンを押し当てて接続します。
LGA1150
LGA1155の後継となるIntelのメインストリーム向けCPUソケット。対応CPUは第4世代Coreシリーズ(Haswell)と第5世代Coreシリーズ(Broadwell)。
LGA1151
LGA1150の後継となるIntelのメインストリーム向けCPUソケット。
対応CPUは第6世代Coreシリーズ(Skylake)第7世代Coreシリーズ(KabyLake)、第8世代Coreシリーズ(CoffeeLake)、第9世代Coreシリーズ(CoffeeLakeRefresh)ですが、第6/第7世代が対応するIntel100/200シリーズチップセットでは第8/第9世代は動作せず、第8/第9世代が対応するIntel300シリーズチップセットでは第6/第7世代は動作しません。
LGA1151ソケットを搭載していてもマザーボードレベルでは完全には互換性がない点に注意が必要です。
LGA1155
Intelの第2、3世代デスクトップ向けCoreシリーズ(SandyBridge/IvyBridge)が採用する新しいCPUパッケージおよびソケット仕様。
既存のデスクトップ向けCPUソケットのLGA1156の後継にあたり、接点数はLGA1156より一つ少ない1,155サイズや接点の密度、CPUクーラーの取り付け方法についてはLGA1156と同じですが、CPUパッケージおよびソケット部分にある切り欠きの位置が異なるため、LGA1155ソケットにLGA1156用のCPUを装着することはできません。
LGA1156
Lynnfield/Clarkdale世代のCorei7/i5/i3シリーズなどで使用されるCPUソケット。
これらのCPUは、パッケージ内にメモリコントローラやPCIExpressコントローラが(一部製品ではGPUも)搭載されるため、それらの信号に必要とされる接点が設けられた結果、前世代にあたるLGA775より端子数が増大しています。
接点の形態はLGA775と共通のLGA(Land Grid Array)、CPU側は接点のみでピンのない構造に、対するソケット側の接点がヒンジ状構造になっています。
LGA775やLGA1366とはCPUクーラーを取り付けるためのリテンションパーツのサイズが異なっているため、LGA1156に対応したCPUクーラーが必要になります。
LGA1366
初代Corei7に採用された1,366ピンのCPUソケット。Corei7では、パッケージが42.5×45mm(ソケットサイズは47.5×50mm)とLGA775タイプのCPUよりもひと回り大きくなり、微細化した40mil(1milは1/1,000インチ、0.0254mm)のピッチで1,366個のパッドが並ぶ。
後期のPentium4以来のLGA775ソケットとは仕様が異なり、CPUクーラーを取り付けるリテンションメカニズムもILM(IndependentLoadingMechanism)に一新されているため、LGA775用のクーラーをそのまま流用することはできません。
LGA2011
2011年に登場した、SandyBridge-EおよびIvyBridge-Eコアを採用したハイエンドCPU「Corei7-3800/3900/4800/4900」シリーズ用のCPUソケット。
LGA2011の性能
PC3-12800 DDR3 SDRAMの4チャンネルアクセスによる51.2GB/sという広いメモリ帯域や、40レーンのPCIExpressをサポートするなど、従来のハイエンドプラットフォームであるLGA1366を大きく上回る性能を持ちます。
LGA2011の特徴
その代わり、対応CPUのパッケージサイズが幅52.5×奥行き45mmと、LGA1366対応CPUのパッケージサイズ(幅42.5×奥行き45mm)よりも大きくなっています。また、従来のLGAソケットとは異なり、二つのレバーを使って固定するようになっているのも特徴です。
CPUクーラーはLGA2011専用、もしくは対応製品しか利用できず、従来のLGA1155/1156/1366対応製品とは互換性を持ちません。
LGA2011-v3
LGA2011の後継となるIntelのハイエンドデスクトップマシン向けCPUソケット。
対応CPUはCorei75800/5900シリーズ(Haswell-E)とCorei7-6800/6900シリーズ(Broadwell-E)。LGA2011と名称が似ていますが、CPUの切り欠きの位置などが異なります。
LGA2066
LGA2011-v3の後継となるIntelのハイエンドデスクトップマシン向けCPUソケット。対応CPUはCoreXシリーズ(KabyLake-X、SkyLake-X、SkyLake-X、Refresh、CascadeLake-X)。
LLC(Last Level Cache)エルエルシー
IntelのSandyBridge以降のマイクロアーキテクチャのCPUが備える3次キャッシュのこと。コアごとに分割されたキャッシュがリングバスで接続されています。
LPDDR(Low Power Double Data Ratememory)エルピーディーディーアール
2003年にアメリカの電子機器規格標準化推進団体のJEDECによって策定された省電カメモリインターフェース。
電源電圧を1.8Vに引き下げることで、2.5V電圧である通常版のDDRSDRAMの機器と比較して大幅に消費電力を抑えることに成功しています。
携帯やスマートホン、モバイル端末などに多く搭載されている「LPDDR」
最大動作周波数166MHz、最大データバス幅32bit、データ転送速度は333Mbpsで、携帯電話やスマートホン、モバイル端末などに多く搭載されています。後述のLPDDR2と区別するために「LPDDR1」と呼ばれることもあります。
2007年「LPDDR2」が策定される
携帯端末の高性能化に伴い、最大動作周波数を533MHzに引き上げることでデータ転送速度を1,066Mbpsにまで高めた「LPDDR2」が2007年にJEDECによって策定されました。電源電圧は1.35V版と1.2V版の2種類が用意され、LPDDRの特徴である低い消費電力は引き続き保たれている。
後継規格として、DDR3ベースのLPDDR3DDR4ベースのLPDDR4などが存在します。
MCH(Memory Controller Hub)エムシーエイチ
Intelが800シリーズのチップセットから採用した「Intel Accelerated Hub Architecture」における、ホストコントローラ側のチップの呼称。
従来のシステムで言う「NorthBridge」に相当。
GMCHは、CPUとメモリまわりの機能にグラフィックスコントローラを統合したチップで、グラフィックスコントローラのないタイプをMCH(Memory Controller Hub)と言います。
現在のシステムではMCHが持っていた多くの機能はCPUに取り込まれています。
OpenCL(Open Computing Language)オープンシーエル
マルチコアCPUやGPUなど、多数の並列処理プロセッサ向けのプログラム開発環境。C言語ベースで、OpenCL Working Groupによって策定されています。
PCH(Platform Controller Hub)ピーシーエイチ
Intel製チップセットの通称。Nehalemコアの一部とSandyBridgeコア以降のCPUと接続される、SouthBridge相当の役割を持ったチップ。
対象となるCPUがNorthBridge相当機能を内蔵するため、1チップで従来の機能をカバーできます。
PCLMULQDQ命令
LGA1156版Corei5シリーズに搭載された新命令。「キャリーなし乗算命令」と呼ばれる(キャリーとは繰り上がりの意味)。AES-NIと同じく、主に暗号化に関する処理の速度の向上を目的とした命令。
Pentiumペンティアム
Intel製CPUブランドの一つ。第5世代のx86系CPUで初めて使われるようになります。
CPUは、当時のほかのパーツ同様、番号で呼ばれていました。
リンク
商標登録の理由から名付けられた「Pentium」
「486」の後継となる第5世代のCPUは、一般には586と呼ばれていましたが、互換CPU訴訟の過程で、単なる数字の羅列に過ぎない名前が商標として認められなかったため、ギリシャ語で「5」を意味する「Pent」に、ラテン語系の名詞語尾「ium」を付けた「Pentium」という名が作られ、リリース前の1992年に発表されます。
Pentiumファミリーの登場
以降しばらくはCPUのアーキテクチャが変わってもハイエンドやメインストリームクラスのCPUにはこのブランドが用いられ、Pentium Pro、Pentium II/III/4/Dといった製品が登場することになります。
2006年、メインストリームは、Coreブランドへ
その後、Intelは2006年にリリースしたCoreブランドへ全面移行する計画でしたが、一部の国や地域においては依然Pentiumブランドのほうがネームバリューが高いため、Core2シリーズの下位ブランドとして復活。2020年現在では、メインストリームクラスのCorei3の下位、エントリークラスのCeleronの上位に位置付けられています。
リンク
Phenomフェノム
2007年11月に登場した、K10アーキテクチャを採用したデスクトップPC向けの新ブランドのCPU。Phenomの名称は「驚異的な目を見張る(Phenomenal)」から取られています。
Phenomファミリー
当初はハイエンドデスクトップ向けクアッドコア「PhenomFX」、パフォーマンスデスクトップ向けクアッドコア「PhenomX4」、エントリー向けデュアルコア「PhenomX2」の製品ラインナップで展開する予定でしたが、デュアルコアがキャンセルされ、クアッドコア製品のコアを一つ無効にしたトリプルコア製品を発表。デュアルコア製品はAthlonX27000シリーズとしてリリースされた。後に製造プロセスが45nmになったPhenomIIシリーズも登場しています。
リンク
Piledriverパイルドライバー
Bulldozerアーキテクチャの第2世代CPUコアの開発コードネーム。FXシリーズから導入されたBulldozerをベースに、分岐予測機構とスケジューラの強化、内部バッファの増量、拡張命令セットのサポート、2次キャッシュの効率改善などが施される。
AMDの場合、CPUコアのアーキテクチャの違いを示す開発コードネームとは別に、CPUやAPUのブランド、アーキテクチャなど、それぞれに開発コードネームがあるため混同されがち。
第2世代Aシリーズは「Trinity」で、「Piledriver」はTrinityのCPUコア部分、「Bulldozer」がCPUコアアーキテクチャといった具合にそれぞれの開発コードネームが付けられています。
同じPiledriverコアを搭載する製品には、第2世代FXシリーズ(Vishera:ビシュラ)がある。
QPI(Quick Path Interconnect)キューピーアイ
Intelが開発しNehalemアーキテクチャのCorei7などに採用したCPU-チップ間のインターフェース。
CSI(CommonSystemInterface)のコードネームで呼ばれていたもので、FSB(FrontSideBus)に代わるCPUの外部バスとしてCPU-チップセット間の接続に使用。
マルチプロセッサ環境では、CPU間の接続にも使われる。インターフェースは、従来のバス型のパラレルインターフェースからPCI Expressなどと似たポイントツーポイント方式のインターフェースに一新され、20レーン(うち16レーンがデータ)とクロック信号の上下ペア(ディファレンシャル信号なので計84本)で1チャンネルを構成します。初期仕様で最大6.4GT/s、一方向あたり12.8GB/sの転送能力を持つ。
リンク
RISC(Reduced Instruction Set Computer)リスク
CPUのアーキテクチャを表わす言葉で、複雑で高度な処理を行なう命令セットを持たせたものをCISC(Complex Instruction Set Computer:シスク)、最小限の単純な命令セットだけを備えたものをRISCと呼びます。
RISCは、個々の命令セットを効率よく高速に実行することを主眼とした設計です。
リンク
CISCの特徴
CISCが備える複雑な命令セットに代わる部分もプログラミングしなければならないため、一般にソフトウェア側にかかる負担が大きくなりますが、CPU自身も含め、高速化しやすいとされています。
ただし、RISC側も命令セットを増やしたり、CISC側も実行クロックを減らしたりと、両者の決定的な差はなくなりつつあります。
CISC、RISC風への進化
x86系CPUは高度で複雑な命令セットを持つ典型的なCISCアーキテクチャでしたが、現在は一つの複雑な命令をCPU内部で複数の単純な命令に展開し、RISC風に実行できるように進化しています。
リンク
Ryzenライゼン
2017年に第1世代が登場したAMDのメインストリーム向けCPUSocket AM4と呼ばれるCPUソケットを採用しています。
Ryzenの特徴
新規に開発されたZenマイクロアーキテクチャで設計されており、コアあたりのスループットが過去のAMD CPUより大幅に向上しているのが特徴。
第3世代からはマイクロアーキテクチャがZen2に進化し、CPUコアとI/Oのダイを分離した上でCPUパッケージ内で接続するチップレットと呼ばれる構造を採用。最大16コアのモデルが用意されています。
SandyBridgeおじさん
2011年に発売されたSandyBridgeコアのCPUを使い続けている自作PCユーザー。
SoC(Systemona Chip)エスオーシー
システムを構成するさまざまな機能を一つに集積したチップ。
Socket AM3+ソケットエーエムスリープラス
Socket AM3+は、AMD FXシリーズに対応するソケットとして、CPUの発表に先駆けて2011年5月から投入されています。ピン数は942ピン。前世代のPhenom II / Athlon IIが採用するSocket AM3とは互換性があり、Socket AM3+マザーボードにSocke tAM3のPhenom IIやAthlon IIを装着して使うことや、その逆も可能です(製品についてはUEFI/BIOSなどの対応が必要)。
Socket AM4ソケットエーエムフォー
Socket AM3+およびSocket FM2+の後継となるAMDのメインストリーム向けCPUソケット。
対応CPUは第1世代Ryzenシリーズ(Summit Ridge、Raven Ridge)、第2世代Ryzenシリーズ(Pinnacle Ridge、Picasso)、第3世代Ryzenシリーズ(Matisse)など。第3世代Ryzenと同時に登場したX570チップセットは第1世代Ryzenシリーズに非対応であるなど、Socket AM4ソケットを搭載していてもマザーボードレベルでは完全には互換性がない点に注意が必要。
Socket FM1 ソケットエフエムワン
Socket FM1はAMDAシリーズ、およびAMDE2シリーズに対応するCPUソケット。Socket AM3/AM3+などほかのAMD CPUのソケットとは互換性がない。中央にブランク部分がある形状をしており、ピン数は905本となっています。
Socket FM2 ソケットエフエムツー
第2世代AシリーズAPUのプラットフォーム(パッケージ及び、ソケットの仕様)。第1世代AシリーズAPUのプラットフォームであるSocket FM1とは互換性がなく、第2世代AシリーズAPUを利用するには、Socket FM2プラットフォームのマザーボードが必要。
Socket FM2ソケットのピン数は904ピンで、Socket FM1(905ピン)より1本少ない。ピンの配置も変更されているため、Socket FM2パッケージのAPUをSocket FM1ソケットに挿すことやその逆もできないようになっています。
SOI(Silicon-On-Insulator)エスオーアイ
ハードチップの製造技術の一つ。絶縁膜の上に回路を組むことによってトランジスタ基板間の不要な容量(寄生容量)を低減し、高速化と省電力化を実現できます。
SRT(Smart Response Technology)エスアールティー
IntelのSandyBridgeアーキテクチャ採用CPU向けチップセット「Z68」以降で搭載されているストレージ関連機能。SSDをHDDのキャッシュとして利用することにより、大容量記録と高速転送の両立を図れます。
リンク
SSE(Streaming SIMD Extensions)エスエスイー
ストリーミングSIMD(シムド)拡張命令。Pentium III以降に搭載されている、Intelのマルチメディア向け拡張命令セット。
複数のデータをまとめて実行する「SIMD」
複数のデータに対し、一度にまとめて同じ命令を実行して処理することをSIMD(Single Instruction Multiple Data)と言います。
繰り返し同じ処理を行なうことの多いマルチメディア系の処理に適しており、CPUの進化に伴って拡張され、SSE2/3/4/4/1/4.2などが存在します。
SSE4aはmAMDが独自に追加した命令で、IntelのSSE4.xのように、XMMレジスタを扱う複合データ型とは直接的な関係はありません。
Tri-Gateトランジスタ トライゲートトランジスタ
Intelが世界に先駆けて開発した3D構造のトランジスタ。従来のプレーナ型トランジスタでは、シリコン基板上にゲートを設け、その両側をソース/ドレイン(電流の送信側/受信側)とする構造であり、電流の通り道であるチャンネルは平面のまま、その距離を縮めてきた。
Tri-Gateトランジスタではシリコン基板上にソース/ドレインとゲートを立体的にかみ合わせたような構造を採ることで、ゲートとチャンネルを3面設けて電流を流れやすくしています。
これまでよりも大幅に低い電圧で、かつ高速に電流のON/OFFを制御できるようになり、アクティブ電流(チャンネルに電流が流れている状態の電流)を大きく低減。構造上チャンネルをシリコン基板から切り離すことができるためリーク電流(シリコン基板を通じてソースからドレインに漏れる電流)の抑制にも大きな効果があり、オフステート時の電力も大幅に低減できます。
Trinityトリニティ
第2世代CPUコアのPiledriverを採用したAMDの第2世代AシリーズAPU(GPU統合型CPU)の開発コードネーム。ノートPC向けラインナップが2012年5月15日に、デスクトップPC向けラインナップは2012年10月2日に発表されました。
Turbo CORE 3.0 Technology(Intel Turbo Boost Technology)
CPUの負荷に応じてコアの動作クロックを安全な範囲内で調整し、高速に処理する「Turbo CORE Technology」の3世代目となる機能。
Phenom II X6シリーズから導入された初代の機能は少数のコア(全コアの半数以下)に負荷が偏っている場合にクロックを向上させるにとどまっていましたが、FXシリーズから導入された2世代目の機能では全コアに負荷がかかっている状態でもクロックが上昇するようになる。
3世代目では、CPUコアのクロックに加えて、GPUコアのクロックも負荷に応じて動的に向上させることができるようになる。
VLIW(Very LongInstruction Word)
プロセッサのマイクロアーキテクチャの一つで、並列に並べた演算器に対して複数の命令を同時に実行させる方式。
VLIWの仕組み
スーパースカラがプログラムをCPU内部のデコーダ/スケジューラで内部命令に分解して並列実行するのに対し、VLIWではあらかじめコンパイラレベル(ドライバレベル)で並列に実行できるように命令をまとめてプロセッサに与えます。
VLIWのメリットとデメリット
VLIWではハードウェアの設計を単純化できるため動作クロックを高速化しやすいメリットがありますが、一般に並列化しにくい汎用プログラムでは効率が悪くなるデメリットがあります。
vPro(Intel vPro Technology)ビープロ、ブイプロ
Intelが2006年に正式発表した、リモート管理とセキュリティ機能を強化した企業内デスクトップPC向けのプラットフォーム。
ハードウェアによるCPUの仮想化機能であるVT(Virtualization Technology)を搭載したCore2Duoと対応チップセットIntelのギガビットイーサネットでシステムを構成。
VTと管理技術のAMT(Active Management Technology)により、OSから独立したハードウェアベースの通信チャンネルを使い、ネットワーク上のPC管理を実現するもの。
従来のソフトウェアエージェントによるリモート管理と異なり、OSの状態に依存せずに管理が可能で、システム情報も不揮発性メモリに記録され、電源のON/OFFに関係なく収集できます。
VT(Virtualization Technology)ブイティー
Intelが開発した、CPUの仮想化技術。1個のCPU上で異なるOSやアプリケーションを実行できます。
x86エックスハチロク
Intelが1978年にリリースした8086と後継CPU全体の総称や、それらCPUの命令セットアーキテクチャを包括する呼称に用いられ、初期の16bit命令セットのみを指す場合も。
8bitCPU(8080など)を拡張する形で16bit化され、過去の資産を継承できる現在の主流CPU。
リンク
Zenゼン
AMDがメインストリーム向けのRyzenシリーズおよびハイエンドデスクトップ向けのRyzen Threadripperシリーズ、サーバー向けのEPYCシリーズで採用しているマイクロアーキテクチャ。
2017年登場の第1世代ではZen、2018年登場の第2世代ではZen+、2019年登場の第3世代ではZen2へと進化。従来のAMD CPUのマイクロアーキテクチャよりもクロックあたりに処理可能な命令数が大きく増加したほか、製造プロセスの縮小に伴いZen2アーキテクチャでは最大CPUコア数が倍増、現在のCPU市場を牽引する存在になっています。
簡易水冷(Closed-Loop/All-In-One Liquid Cooling)
簡易水冷キットのこと。PCの水冷システムのうち、水冷パーツ同士をパイプで接続し冷却液も封入済みの状態で販売されているパーツ。
クーラー自体の組み立てと、運用中のメンテナンスが不要である点がメリット。
リンク
本格水冷
対義的な存在として、各種水冷パーツをユーザーが一つ一つ組み合わせて構築したものを本格水冷と呼びます。
キャッシュCache
CPUのキャッシュについて
一般的なPCシステムでは、メモリアクセスを高速化するために、CPUのコアとメインメモリ間に高速なRAMを置き、コードやデータを一時的に記憶しておくキャッシングという手法が用いられます。
キャッシング用のメモリが複数段置かれている場合は、CPUに一番近いものから順に1次キャッシュ、2次キャッシュと呼んでいます。
CPUキャッシュの仕組み
キャッシングは、速度の違う二つのデバイス間の速度差を埋める手法であり、メインメモリに使われているDRAMのアクセスは、CPUの処理速度に比べてはるかに低速であるため、DRAMのスピードに合わせて処理を行なうと、アクセスのたびにCPUが待たされ、システムパフォーマンスが著しく低下してしまいます。
そこで、高速にアクセスできる少量のメモリを用意し、CPUが頻繁にアクセスするコードやデータを率先して蓄えておくようにします(これを制御するチップやモジュールをキャッシュコントローラと言う)。
必要なものが高速にアクセスできるキャッシュ上にある場合には、遅いメインメモリから読み出す必要がないため、処理速度が向上します。また、キャッシュはメインメモリの読み出しだけでなく、書き込みに対しても有効に機能する。
リンク
極冷(LiquidNitrogenCooling)キョクレイ
ドライアイスやLN2(液体窒素)といった極端に低温の気体や液体によってパーツの冷却を行なうこと。
リンク
究極のオーバークロックを狙う「極冷」
究極のオーバークロックを実現するために、ごく一部のユーザーが用いますが、そのためには殻割りや入念な結露対策も必要になり、当然ながら故障率も跳ね上がります。
空冷(AirCooling)
空気との熱交換により目的物を冷却する方法のこと。熱が温度の高いところから低いところへ伝わる性質を利用した「自然空冷」と、ファンなどを使って空気を熱源に吹き付ける「強制空冷」があり、一般的にはこの二つの空冷方式を組み合わせた冷却が行なわれています。
熱が空気に触れる表面積を広くすることで、効率的に冷やすことができるようヒートシンクやヒートパイプ、ファンといった部品を組み合わせて利用しています。
リンク
コア欠け
現在のCPUはヒートスプレッダと呼ばれる金属プレートが装着された状態で販売されていますが、Pentium IIIやAthlonといったかつてCPUでは、CPUコアを含むダイと呼ばれる小型のチップが表面に露出しているのが一般的でした。
オーバークロックブーム
当時はCPUのオーバークロックがブームになった時代でもあり、CPUを冷却するためのヒートシンクをユーザーが取り付ける際、接触の度合いを高めようとネジを締め込み過ぎるなどによってダイの角や縁に大きな力がかかり、結果としてダイの一部が欠けてしまうという事故がめずらしくなかった。これをコア欠けと呼びます。
現在でも一部のオーバークロッカーは冷却効率をよくするためにヒートスプレッダを外し、ダイに直接ヒートシンクを接触させますが、この際にもコア欠けの危険性があります。
リンク
サイドフロー(Side-Flow)
空冷CPUクーラーの形状の1種。マザーボード面に対して垂直にファンを取り付け、CPUクーラー側面からヒートシンクに向けて空気の流れを作るタイプのこと。
ヒートシンク及び、ファンの大型化が比較的容易である他、PCケースの前面から外気を取り込んで背面から排熱するという理想的なエアフローを構築しやすいのがメリット。
2基のファンでヒートシンクを挟み込む、ヒートシンクをツインタワー化して1〜3基のファンを取り付ける、といった大型製品もあります。
シリコングリス(Silicon Grease)
放熱の大きなチップや部品にはヒートシンクを取り付けて冷却しますが、それらの表面は平らなように見えて微細な凸凹が存在します。そのままの状態で両者を接触させても凸凹部分にたまった空気により熱の移動が阻害されてしまうため、熱伝導率のよい素材でその凸凹を埋めることで冷却効率は大きく向上します。
その素材として一般的なのが半固体のシリコングリスで、さまざまな種類のもの発売されています。同じ目的でグリスではない形態のものもあり、シート状に加工されたサーマルパッドや液体金属などが利用されています。
リンク
チップセット
広義では、複数のチップを組み合わせてまとまった機能を提供するものを指しますが、PCでは、マザーボードに必要な機能を1〜数個のチップにまとめたものを、特にチップセットと呼んでいます。
古くは、汎用チップの組み合わせで個々の機能を実装していましたが、近年はチップセットの主要機能の一部はCPUに内蔵され、残った機能が集約された結果1チップ構成となっていくという技術の革新の流れがあります。
チップレット(Chiplet)
CPUにおいて、CPUコアとI/Oのダイを分離した上でCPUパッケージ内で接続する構造のこと。2019年に登場したZen2マイクロアーキテクチャのAMD CPUが採用されています。
CPUコアを搭載したダイは最先端ですが高コストな7nmプロセスで製造し、I/Oやメモリインターフェースなどを搭載したI/Oダイは成熟して低コストな14nmプロセスで製造するなど、CPU全体のサイズやコストの低減に効果が大きく、64コアのような超メニーコアCPUの実現にもこのチップレット構造が寄与しています。
直接接触式ヒートパイプ(Direct Touch Heatpipe)
CPUなど高温の熱源に直接接触させることで熱移動の高速化を図ったヒートパイプ。
ヒートパイプは、パイプ状の金属に揮発性の液体(作動液)を封入した熱伝達部品。加熱部と放熱部で起こる作動液の相変化(気化⇔液化)を利用して、離れた場所に高速かつ大量に熱移動を行なえる性質があります。
CPUクーラーではヒートシンクのベース部分に埋め込んで使われることが一般的でしたが、加熱部分の温度が高いほど温度差が高まり熱移動も高速化することから、CPUのヒートスプレッダにヒートパイプを直接接触させる製品も増えています。
適切な効果を得るには接触面が十分に平滑で、かつ放熱部の冷却能力が十分にあることが条件になります。
リンク
トップフロー(Top-Flow)
空冷CPUクーラーの形状の1種。マザーボード面に対して水平にファンを取り付け、CPUクーラー上部からヒートシンクに向けて空気の流れを作るタイプのことを指します。
CPUクーラー全体の高さを抑えつつ、十分な冷却性能を確保できるのが特徴。大型の製品の場合、CPUだけでなく、CPU周囲の部品類(VRM)などの放熱にも効果が期待できるものもあります。
代表的な製品は、IntelおよびAMDのCPU付属CPUクーラーなど。
熱交換器(Heat Exchanger)
熱を移動させ効率的に冷却(CPUの場合)することを目的とした放熱部品。
リンク
パイプライン(Pipeline)
命令の実行に必要な処理を小さなステップに分け、それぞれを個別のユニットが流れ作業のように処理していくことによって、CPUの処理速度を向上させる技術。
リンク
ヒートシンク(Heat Sink)
CPUをはじめ、発熱量の多いチップに取り付けられる、アルミなどで作られた金属板。
空気中に効率よく熱を逃がすため、表面にフィンと呼ばれる多数の薄い板を持たせて表面積を大きく取るものが多い。CPUに取り付けるタイプはCPUクーラーとも呼ばれ、ヒートシンクとファンを併用したものが一般的。
リンク
ヒートスプレッダ(Heat Spreader)
熱を拡散(放熱面の拡大)させて放熱効果を高める、金属などでできた放熱板。
ヒートシンクが取り付けられない場所(メモリモジュールなど)での放熱に使われる他、パッケージ本体をヒートスプレッダで覆ったチップもある(CPUやGPUに利用)。
ヒートシンクに効率よく熱を伝える目的で、熱伝導率の高い銅板などをヒートシンクとの間に挟んで使用することも多く、一部の製品では、ヒートシンク自体に埋め込まれています。
ヒートパイプ(Heat Pipe)
パイプの内側に、細かな網目状の素材(ウィック)を貼り、その中を真空にして内部にわずかな液体(作動液)を封入したもの。
一方の端で液が加熱されて蒸発、管内の圧力差でもう一方へ移動した後、冷えて液化した作動液が、毛細管現象を利用して戻ってくる仕組みで、熱を移動させる仕組み。
リンク
ピン折れ
PGAと呼ばれるタイプのパッケージを採用したCPUの裏側には、CPU側の基板とマザーボード側のCPUソケットを電気的に接続するためのピンが用意されています。これを誤って折ってしまうことをピン折れ、曲げてしまうことをピン曲げと呼ばれています。
AMDのRyzenシリーズは最新の第3世代でもPGAタイプであり、CPUの取り付け・保管の際にはピン折れ曲げの危険性があります。IntelのCPUはCPU側には接点しか持たないLGAと呼ばれるパッケージに移行しています
リンク
プロセスルール(ProcessRule)
チップ内部の最小回路(配線)幅。製造プロセス、あるいは単にプロセスとも。
チップの製造方法
チップは、ウエハーと呼ばれるシリコンの薄い基板上に回路パターンを形成し、部分的に不純物を注入して微細なトランジスタを形成していきます。パターンの形成は、写真の焼き付けとよく似た方法で行なわれ、フォトマスク(回路が描かれたネガに相当)を介し、ウエハーを露光させてレンズで縮小したパターンを焼き付けますが、この時フォトマスクをどれくらい縮小できるかによって回路幅が決まります。
表記はμmやnmで示され、たとえば1μmなら1mmあたり1,000本の配線が形成できます。
同じマスクを用いても、より細かいプロセスルールで製造すれば、その分ダイサイズは縮小、これにより1枚のウエハーからより多くのチップが製造でき、消費電力も削減、発熱量も低下します。
さらに、回路をON/OFFするスイッチの役目をになっているCPU内部のトランジスタは、サイズが縮小されることでスイッチ間(ゲート長と言う)が短くなり、より高速に動作可能に。動作周波数の向上にも、プロセスルールが大きく貢献します。
リンク
プロセッサー・ナンバー(Processor Number)
Intelが2004年にリリースした90nmプロセスのPentiumM(Dothan)から採用した、CPUのクラス(機能)とグレード(性能)の違いを表わす3〜5桁のアルファベットや数字。
ペルチェ素子(PeltierDevice)
異なる種類の導体(金属など)に電流を流すと、熱伝導率の違いにより熱移動が起こる「ペルチェ効果」(Peltiereffect)を利用した熱電(冷却)素子。
2枚の金属でP型半導体とN型半導体を挟み込んだような構造になっており、直流電流を流すと一方の金属から反対面の金属へ熱の移動が起こります。
電流の極性を逆転させるとその関係を反転させることができるため、加熱にも冷却にも利用でき、温度制御も可能となっています。複数枚を重ねて使うことで冷却効果を増大させることができます。
素子自体の発熱量が大きく、その冷却には気を使う必要がありますが、小型で振動も発生しないことからCPUクーラーのほか、携帯用の冷温機などに使われています。
本格水冷(Open-Loop Liquid Cooling)
水または冷却液を媒体として冷却を行なう仕組み。
PC内のCPUやマザーボード、ビデオカードといった発熱の大きなパーツに内部を冷却液が流れる水冷ヘッドと呼ばれる金属部品を取り付け、熱を奪った冷却液をポンプとパイプによって循環させ、ファンを取り付けたラジエータと呼ばれる放熱器から熱を放出します。
冷却液の量が冷却性能に影響するため、大型のリザーバタンクを取り付けることもあります。
リンク
マイクロアーキテクチャ(Microarchitecture)
演算ユニットやパイプライン、各種制御など、CPUが命令を実行するための内部構造。
第n世代と呼ばれるCPUの基盤となる基本設計で、16bit時代の8086(第1世代)、80286(第2世代)ではIntel、AMDともに同一でしたが、386(第3世代)からは分岐することに。
AMD、リバースエンジニアリングにより互換CPUを提供
AMDはリバースエンジニアリングにより同機能のCPUにIntelのマイクロコード(命令セットを実際に実行する内部命令)を搭載する手法で互換CPUを提供。
その後のP5(Intel) / K5(AMD)はそれぞれ独自のアーキテクチャですが、命令セットアーキテクチャは独自拡張の一部を除いて共通しており、同じプログラムの実行環境を提供していました。
マルチCPU(Multi CPU)
複数のCPUを使うマルチプロセッシング技術を使ったシステムの一つ。このうちデュアルCPUは、2個のCPUを搭載したタイプ。
マルチコアCPU(Multi-Core CPU)
単一チップ上に複数のコア(CPUの中核となる回路)を実装したCPUをマルチコアCPUと言い、二つのコアを搭載したタイプをデュアルコアCPU、四つのコアを搭載したタイプをクアッドコアCPUと言います。
デュアルコアCPUは、2個のCPUを搭載したデュアルCPUと同等のことを単一チップで実現し、高速化を図ります。
2005年、デュアルコアCPU時代が到来
2005年4月、IntelがPentium Extreme Editionをリリース。5月には、AMDがデュアルコアOpteronとAthlon64X2を、Intel PentiumDをラインナップに加え、PCにデュアルコアCPU時代が到来します。
2020年には64コアに到達
以降のx86系CPUは4コア、8コアとコア数を増やしており、2020年に登場したAMD Ryzen Threadripper 3990Xでは64コアに到達した。マルチCPUやマルチコアCPU環境では、個々のスレッドを個別のCPUやCPUコアに振り分けて並列実行することで処理を高速化します。
その実現には、スレッドを複数のCPUに振り分ける機能を持った、マルチプロセッサ対応のOSが必須です。
リンク
ムーアの法則(Moore’s Law)
Intelの創設者の一人GordonE.Moore(ゴードン・ムーア)が唱えた、「一つのチップに集積できるトランジスタ数は18〜24カ月で2倍になる」という予測。
Mooreは、故Robert Noyce(ロバート・ノイス)とともに1968年にIntelを創設。第2代CEO(1975〜1987)を経て、現在は同社の名誉会長を務めています。
ムーア、1965年に発表された論文で「集積度は、1年で2倍になる」と予想
1965年、Fairchild Semiconductor在籍当時のMooreは「Electronics Magazine」誌(1965年4月19日号)に寄せた論文「Cramming more components onto integrated circuits」において、「コストパフォーマンスのよい集積度は、1年で2倍になる」と予想。
当時は、まだ50コンポーネントを超えたところにあったICの集積度が、5年後には1,000を超え、10年後には6万5,000コンポーネントに達するであろうと述べています。
これがムーアの法則の原典で、後に「1年で2倍」を「2年で2倍」に改訂し現在にいたっています。
経験則から生み出されたムーアの法則
このムーアの法則は、科学的な根拠にもとづいた法則ではなく、いわゆる経験則から生み出されたものであり、その後の半導体技術は、おおむねムーアの予想に沿った勢いで進歩し、18~24カ月ごとに新しい技術で作られた、高密度で高速なチップが登場。半導体産業の技術革新の指標となっています。
命令セットアーキテクチャ
命令セットやレジスタなどのプログラミングにかかわるCPUの基本設計。
内部構造が異なっても、命令セットが同じなら互換CPUとして機能、IntelやAMDのCPUは、既存の命令セットを継承する形で拡張されており、過去のプログラムもそのまま利用可能。
モデルナンバー(Model Number)
AMDが2001年にリリースしたAthlon XPから採用した、CPUの基本性能とクロックを考慮したパフォーマンス値、もしくは、CPUのクラス(機能)やグレード(性能)の違いを表わすアルファベットや数字。
リンク
リテールクーラー(Retail Cooler)
CPUを購入すると化粧箱に同梱されている純正CPUクーラーのこと。この呼び名は和製英語であり、IntelやAMDのデータシートでは単に「サーマル・ソリューション」と言います。
CPUを定格で使用する分には問題なく冷却できる性能を備えているが、動作音は比較的大きめであることが多いです。
それを嫌ってPCを自作するユーザーにはサードパーティ製のCPUクーラーを別途購入するものが少なくなく、そうした状況を受けてCPUメーカー側も、ハイエンドクラスのCPUにはクーラーを同梱しないものが増えている他、LEDで発光するなど自作PCのトレンドをリテールクーラーに取り込む動きも見られます。
リンク
レジスタ(Register)
CPUが演算などの処理を行なう際にデータをCPU内部に一時記憶する極小のメモリで、演算の値や結果、次に実行するプログラムの位置など、処理上必要な多くの情報を格納します。
CPUのbit数を表わす基準は沢山ありますが、一般には整数演算や論理演算を行なうALU(ArithmeticandLogicalUnit:算術論理演算装置)のbit数で表わされ、x86系CPUは、互換性維持のため旧来のレジスタを拡張する形でそれに応じたレジスタを用意します。
8bit時代のアキュムレータ「Aレジスタ」に8bitを継ぎ足した「AXレジスタ」、さらに16bitを継ぎ足した「EAXレジスタ」。64bit版の「RAXレジスタ」となります。